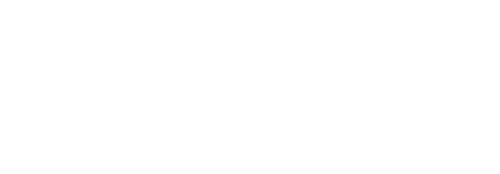開業届を作成したけど、どうやって税務署に提出すればいいんだろう?
ビジネスを始める際には、仕事を頑張ることも大事ですが、今まで知らなかったいろんな種類の事務手続きには頭を悩ませることも多いかと思います。
そのような事務手続きの一つで、特に重要なのが「開業届」の提出です。これは、自分のビジネスを創業する際に、税務署に対して開業の届け出を行う手続きのことを指します。
この記事では、初めて開業届を作成する人向けに
- 開業届の提出場所
- 開業届の提出方法
- 開業届の作成
- 開業届の提出期限
- 開業届を出すメリット・デメリット
について解説していきます。
記事を読めば、開業届をどこにどのような方法で提出すればいいか、提出するために何を準備すればいいかについてわかります。
難しそうに見えて、簡単な作業なので、ぜひ記事を参考にして開業手続きをしてください。
開業届の提出先は納税地を管轄する税務署
開業届を作成した後は、国に提出する必要があります。
気になる開業届の提出先ですが、申請者の納税地を管轄している税務署です。
日本国内にはエリアごとに11か所の国税局と、沖縄の国税事務所1か所があり、それぞれに税務署があります。
| 国税局 | 管轄する都道府県 |
|---|---|
| 札幌国税局 | 北海道 |
| 仙台国税局 | 福島県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
| 関東信越国税局 | 茨城県、栃木県、群馬県 、埼玉県 、新潟県 、長野県 |
| 東京国税局 | 東京都 、千葉県 、神奈川県 、山梨県 |
| 金沢国税局 | 石川県 、富山県 、福井県 |
| 名古屋国税局 | 愛知県 、岐阜県 、静岡県 、三重県 |
| 大阪国税局 | 大阪府 、滋賀県 、京都府 、兵庫県、奈良県 、和歌山県 |
| 広島国税局 | 広島県 、鳥取県 、島根県 、岡山県 、山口県 |
| 高松国税局 | 香川県 、愛媛県 、徳島県 、高知県 |
| 福岡国税局 | 福岡県 、佐賀県 、長崎県 |
| 熊本国税局 | 熊本県 、大分県 、宮崎県 、鹿児島県 |
| 沖縄国税事務所 | 沖縄県 |
都道府県によって、税務署の数は違いますが、いくつかの市町村ごとに1つしかないため、人によっては税務署が自宅から遠くにある場合もあります。
確定申告をしたことがある人は税務署の場所を知っていると思いますが、今まで税務署に行ったことがない人は、自分が住んでいる場所を管轄している税務署の場所を知らないでしょう。
その場合は、国税庁のサイトで、開業届を提出する税務署の場所を調べることができるので、下記のサイトにアクセスして調べてください。
開業届の提出方法と必要なもの
開業届を税務署に提出する場合、以下の3つの提出方法があります。
どの方法で提出してもいいですが、提出方法によって必要なものが違います。
提出方法ごとに必要なものを簡単にまとめると以下のようになります。
| 物\提出方法 | 直接提出 | 郵送で提出 | 電子申告 |
|---|---|---|---|
| 印鑑 | 必要 | 必要 | 必要なし |
| プリンター | 必要 | 必要 | 必要なし |
| マイナンバーカード | ある方が便利 | ある方が便利 | 必要 |
| 封筒・切手 | 必要なし | 必要 | 必要なし |
| 電子カードリーダー | 必要なし | 必要なし | 必要 |
税務署が近くにあって、行く時間がある人は直接税務署に提出するのがおすすめ。
税務署が遠かったり、行く時間がない人は、封筒や切手を用意する必要がありますが、郵送しましょう。
電子申告が1番簡単ですが、マイナンバーカードや電子カードリーダーを持っている人しかできません。
ではそれぞれの提出方法について詳しく説明していきます。
税務署に直接提出する
まず最初に紹介する提出方法は、税務署に行き、開業届を提出する方法です。
直接提出する人は
- 作成した開業書類一式
- 本人確認書類(「マイナンバーカード」または「通知カード・住民票+顔写真付き本人確認書類」
を準備して行きましょう。
税務署に行く時は、書類の控えも忘れずに持っていくようにしましょう。
窓口で提出すると、本人確認され、押印された書類が返却されれば完了です。
僕の場合は1分ほどで完了しました。
税務署に行く手間はかかりますが、必要なものも少なく、税務署での提出にかかる時間は一瞬なので、税務署に行ける人はこの方法がおすすめです。



税務署は平日の朝から夕方までしか開いてない。
休日は閉まっているので、平日に提出できないサラリーマンで副業する人などは以下で説明する「郵送」または「電子申告」になりますね。
税務署に郵送する
税務署に郵送する場合は以下のものを準備しましょう。
- 作成した開業書類一式
- 本人確認書類のコピー(「マイナンバーカード」または「通知カード・住民票+顔写真付き本人確認書類」
- 返信用封筒2つ
- 切手2つ
郵送するため「封筒」と「切手」が必要になります。
また、「申請者が税務署に郵送する用」と「税務署から返却される用」で、2つずつ必要です。
税務署の宛先と差出人を記入し、切手を貼った封筒に
- 書類一式
- 本人確認書類のコピー
- 切手を貼りつけた返信用封筒1つ
を入れて郵送しましょう。
返信用封筒には、切手を貼り、自分の住所と名前を記載して同封するようにしましょう。
また、郵送の場合も、控えも忘れずに同封して郵送するようにしてください。



封筒と切手、本人確認書類のコピーを用意しないといけないのが面倒くさいけど、直接税務署に行く手間は省けるね!
電子申告する
開業届を電子申告で提出する方法は簡単ですが、
- マイナンバーカード
- PC
- ICカードリーダー
の3つを全て持っていないといけません。
また、電子申告に対応しているサービスを使って開業届を作成する必要があります。
僕自身は毎年会計freee



電子申告は作成から提出までオンラインで完結するので、利用できる人は電子申告での提出がおすすめ!
開業届の作成について
開業届は以下の3つの方法で入手することができます。
どの方法を使ってもいいですが、おすすめはfreee開業を利用する方法です。
なぜなら、自分で取ってきたり、ダウンロードして記入する場合は、開業届の記入項目についてネットで調べながら記入する必要があります。
それに対し、freee開業なら、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで開業届が完成するからです。
誰でも5分もあれば作れます。
調べながら記入する場合、記入間違えをする可能性がありますよね。
freee開業であれば、入力した項目が自動的に正しい位置に印刷されます。
そして、作成された書類一式にマイナンバーを書いて、印鑑を押印するだけなので失敗することがありません。
つまり、freee開業を使えば、開業届の書き方の知識がない人でも失敗することなく簡単に開業届が作成できるということです。
無料で使えるので、ぜひ使ってみてください。
freee開業についての詳細、使い方に関しては以下の記事を参考にしてください。
開業届はいつまでに出さないといけないのか
「開業届を出さなければならないのはわかったけど、その期限はいつなのだろう?」と疑問に思うことがあるかもしれません。
そこで、開業届の提出期限について詳しく解説していきます。
開業届の提出期限は開業から1カ月以内
開業届の提出期限は「開業から1カ月以内」となっています。新しい事業を始める決意をしたら、その事業を始めた日を含めて1カ月以内に、最寄りの税務署に開業届を提出しましょう。
「1カ月以内」という期間は、意外と短く感じるかもしれませんね。
開業後はやるべきことが山積みになっている状況だと思いますが、税金の計算が滞ったりするため、開業届の提出は忘れてはいけません。
開業届は後から出しても大丈夫
忙しくて開業届の提出の締め切りである「1カ月以内」を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
「罰せられるのでは?」と心配するかもしれませんが、まず安心してほしいのが、開業届は後から出しても過去に遡って開業日を登録することができる、ということです。
つまり、振り返ってみて「あ、開業届を出し忘れていた!」と気づいた場合でも、開業届は出すことが可能なのです。
したがって、開業から1カ月以上経っていた場合は、すぐに提出するようにしましょう。



税金の問題を未然に防ぐためにも、開業後すぐにでも税務署に開業届の提出をしよう!
開業届を出すメリットとデメリット
自分のビジネスを立ち上げ、フリーランスとして独立する際に提出する「開業届」を出すメリットとデメリットは何か、これから具体的に説明しましょう。
最初に言っておきますが、開業届の提出は義務なので、提出しないといけません。
開業届を出すメリット
開業届を出す事のメリットで最初に挙げられるのは、やはり「税金の節税」の面から考えると、一定の収入が見込まれるフリーランスとしては有利な選択肢となります。
たとえば、自宅を仕事場とする場合、家賃や水道光熱費などが経費として計上できる場合があります。これにより、節税効果が見込まれ、実質的な収入を底上げすることができます。
また、青色申告を電子申告する場合は、最大65万円の控除を受けることができます。
次に、ビジネスを始めたことの「証明」にもなります。自分がビジネスを開始した事実を公に示すことで、お客様や取引先からの信頼を得やすくなるかもしれません。公的な手続きを経て開業したことは、ビジネスパートナーへの信頼構築に寄与します。
自分の屋号名義で銀行口座も解説できるようになります。
更には、「社会保険」の面でもメリットがあります。開業届を提出したことで、国民健康保険や国民年金の自己負担額が減額される可能性もあります。
自治体によって違うので、自分の住んでいる場所を管轄する税務署の公式サイトなどを確認してください。
最後に、「事業経費の範囲が広がる」というメリットもあります。フリーランスとして開業届を提出すれば、その事業に必要な費用の一部を経費として計上できる可能性が広がります。これにより、個人での活動よりも経費を多く計上できるため、税金を節約できる可能性が高まります。



個人事業主向けの補助金や助成金の申請もできるようになるよ!
開業届を出すデメリット
一方、開業届を出すことにはデメリットも存在します。それらは「手間のかかる手続き」、「複雑な税務」などが主な要素となります。
手続きの手間については、一個人として活動するよりも、開業届を出すという手続きには時間とエネルギーが必要となります。書類作成や提出、必要な証明書の取得など、少なからず負担が伴います。
税務が複雑になるという点では、所得税だけでなく消費税の申告も必要となり、確定申告がより複雑になる可能性があります。また、確定申告に関連する書類作成や記帳の習慣も必要となるため、これらの作業に対応する能力や時間が求められるでしょう。
他にも、健康保険の扶養者から外れる可能性や、失業手当が受給できなくなる可能性があります。



フリーランスとして開業する場合はメリットの方が大きいから、必ず開業届を提出しよう!
開業届の提出方法と必要なものまとめ
開業届の提出先、提出方法、提出に必要なものについて解説しました。
ぜひ記事を参考に開業届を作成し、提出してください。
フリーランスとして開業する際には、開業届の提出だけでなく、自身のビジネス形態に応じた確定申告などの税務手続きも必要となることを忘れないようにしましょう。
それらに関する知識もしっかりと身につけて、フリーランスとして活躍する準備を整えてください。